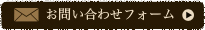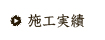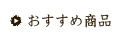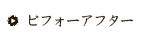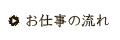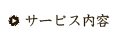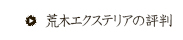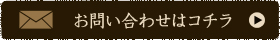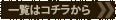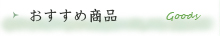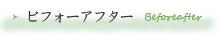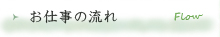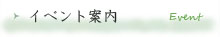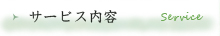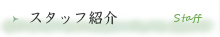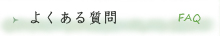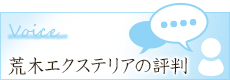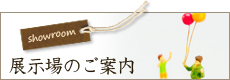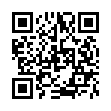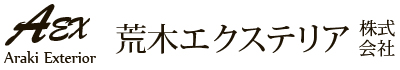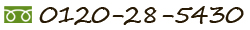今日は冬至
 冬至(とうじ)って
冬至(とうじ)って
二十四節気の一つ。旧暦十一月子(ね)の月の中気で、新暦の十二月二十二~三日頃です。
この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなります。そのため昼が一年中で一番短く、
夜が長くなります。
この日を境に日は徐々にのびていきます。 なのでこの日は冬至かぼちゃを食べて金運を祈り、
冬至風呂(柚子湯)に入って無病息災を祈る行事を各家庭で行います。
 ゆず湯
ゆず湯
ゆず湯に入ると肌がスベスベになる美肌効果があったり、冷え性やリュウマチにも効くし、
体が温まってカゼをひかないとも言われています。
これらの効能は、ゆずに含まれている芳香成分――精油の働きによるものでゆずの精油にはピネン、シトラール、リモネンなどの物質があって、これらは新陳代謝を活発にして血管を拡張させて血行を促進。
ノミリンなどには鎮痛・殺菌作用があるので、体が温まり、カゼも治るのです。
また、ゆずにも含まれているビタミンCが肌にいいことは広く知られており、リモネンは皮膚に膜を作って、肌の水分を逃がさないようになっています。
他にも香りのいいゆず湯はアロマテラピーのリラックス効果も期待できます。
でも、何故、冬至に風呂なのでしょうか ?
この答えは「とうじ」という言葉にあるのです。 冬至の読みは「とうじ」。というわけで、湯につかって病を治す「湯治(とうじ)」にかけています。
更に「柚(ゆず)」も「融通(ゆうずう)が利(き)きますように」という願いが込められているのです。
5月5日に「菖蒲(しょうぶ)湯」に入るのも、「(我が子が)勝負強くなりますように」という、ゆず湯と同じ「願かけ」なのです。
 かぼちゃ
かぼちゃ
「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」 といわれますがなぜでしょうか?
現在は野菜が季節に関係なく供給されていますが、西洋野菜が日本に入るまでこの時期に取れる野菜は少なく、保存できる野菜も少なかったのです。
かぼちゃは保存がきき、保存中の栄養素の損失が他の野菜に比べて少ない。
そのため、冬至の時期の貴重な栄養源でもありました。
かぼちゃの栄養成分の特徴は、なんといってもカロチンを多く含んでいることです。
カロチンは、体内でビタミンAにかわって肌や粘膜を丈夫にし、感染症などに対する抵抗力をつけてくれます。
この時期は栄養を、休養を取って新しい年を元気いっぱいで迎えたいものですね~
 きゅうりのゆずあえ
きゅうりのゆずあえ ~ゆずを使って箸休めにいかがですか?
~ゆずを使って箸休めにいかがですか?
材料(2人分)
きゅうり 1本
塩 少々
めんつゆ 小さじ1
かつおぶし 小1袋(1.5g)
ゆずの皮 適量
作り方:
きゅうりは縦半分に切り、斜めの薄切りにする。
薄切りにしたきゅうりを塩少々でもみ、軽く絞る。
めんつゆ、かつおぶし、と混ぜて皿に盛る。
ゆずの皮を千切りにして上に持って出来上がり。
 鶏のスペアリブ ゆずソース
鶏のスペアリブ ゆずソース
材料(3~4人分)
鶏スペアリブ (なければ手羽中) 16本~20本(約300グラム)
★ゆずジャム またはゆずはちみつ 大さじ2
★薄口しょうゆ 大さじ2
★酒 大さじ2
★水 100cc
★塩 少々
付け合せ
ブロッコリー 1房
プチトマト 6個位
シメジ 1パック
塩 少々
作り方:
①鶏スペアリブ(手羽中)に塩を少々振っておく。
②スペアリブ(手羽中)をフライパン等で焼き皮に軽く焦げ目をつける
③鍋に ★の材料をすべて入れ 火にかける。
④沸騰したらスペアリブ(手羽中)を入れる。
⑤強火のまま煮立たせ、焦げ付かないように箸で軽く転がしながら煮詰める。
⑥スペアリブ(手羽中)を皿に盛りつけ、残った煮汁をかけて出来上がり。
(付け合せ)
ブロッコリーは洗って小房に分け 塩少々入れて沸騰させた鍋でゆでる。
シメジは フライパンにバターを溶かして 洗って小分けにしてソテーする。
プチトマトは 洗ってへたをとっておく
鶏を盛り付けたお皿にそれぞれを盛り付けて出来上がり。